「あのね」
と彼女は、メロンソーダの氷の上に浮かんでいるチェリーを眺めて言った。
「私、こういう時間って、なぜか後からよく思い出すのよ。」
4月の終わり。
僕らは休暇で古くからある保養地にいた。
遅い朝ごはんの後、海沿いを散歩して海岸が見えるレトロな喫茶店に入って、窓際でボンヤリと海を眺めていた。
「あ、なんとなくわかりますね。そういうの。」
と僕が言うと、彼女は「またテキトーに答えたでしょ」と少し笑って、ソーダの泡がくっついて大きくなり、ぷくぷくと浮かんでいくのを眺めながら言った。
「別になにか大きなイベントなわけでもないけど、私の脳は、ちゃんとそれを大事なものだと認識して、
こういう風景を”大事なもの”を入れておく引き出しに保存していく。
自分の履歴書を作るなら、そういう”大事なもの”を引き出しから取り出して、
写真にして並べたら、本当の自分が一番良くわかる履歴書ができるように思う。」
そこまで言うと、彼女はチェリーをぱくっと口に放り込んだ。
僕は彼女の口元を見ながら、「その中にどのくらい僕の写真が入ってるんでしょうね」と言うと、彼女は少し驚いたような顔になって言った。
「あなたがそんな風に言うとは思わなかったわ。」
「変ですか?」
「ううん。そうじゃなくて。」
彼女は海岸沿いを歩く老夫婦に少し目をやった後、半分くらいになったメロンソーダの氷をかき混ぜてから、
「ちょっと嬉しいかな。」
と言った。
4月の終わりのメロンソーダ。
僕らは海沿いの古い喫茶店の少し暗い窓際で、ひっそりと ”大事なもの” を作り続けていた。

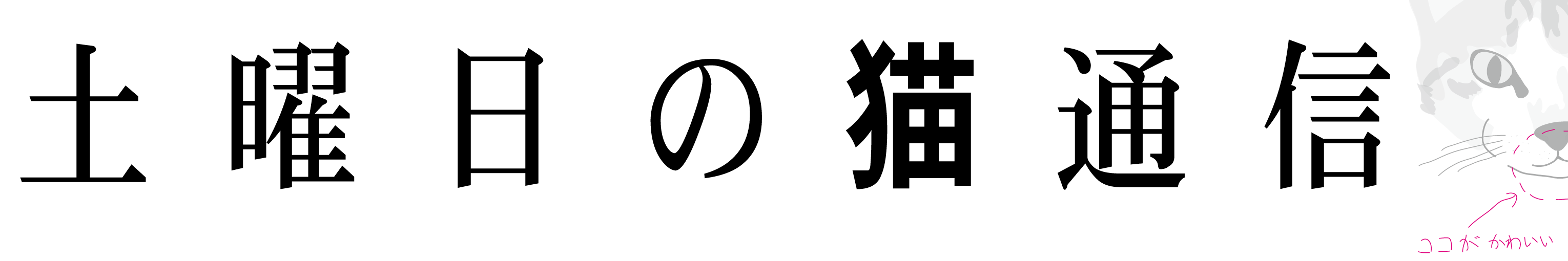
コメント